
三重奏の果実
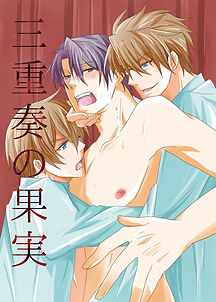
「で、どっちにするんだ、御堂?」
「どちらにするんですか、孝典さん?」
左右から名前を呼ばれて、御堂は瞼を押し上げた。
どうやら、うたた寝をしていたようだ。飲み過ぎたのだろうか、どこか現実感に欠けたようなふわふわとした心地だった。覚醒しきらないぼんやりとした思考のまま状況を確認すれば、御堂は左右の人物に挟まれるようにして、ベッドの端に腰を掛けていた。
右を見ると、佐伯克哉がいた。端正に整った顔立ちを銀のフレームの眼鏡が引き締めている。佐伯は御堂と視線が合うとにやりと笑って眼鏡のレンズを押し上げた。
左を見ると、佐伯克哉がいた。右の佐伯克哉と同じ整った顔立ちだが、こちらは眼鏡をかけていない。下ろされた前髪がかかる柔らかな眼差しが御堂を見つめている。克哉は御堂と視線が合うとふわりと微笑んだ。
御堂は混乱しながらもう一度左右を見比べて、前を向いた。額に手の甲を当てて呆然と呟いた。
「どういうことだ、これは」
「どういうことも何も、あんたには、俺たちのどちらかを選んでもらわないと。《俺》か、《オレ》か……。決められないなら俺が決めてもいいが」
そう言って、右側に座る佐伯は御堂の肩をぐいと抱き寄せた。そう、この強引さはまさしく佐伯だ。佐伯の右手が御堂の顎を掴んだ。真正面から覗き込まれる。
佐伯の眼鏡のレンズに自分の顔が映り込み、重なる視線に鼓動が跳ね上がった。佐伯の顔が近づいてくる。しかし、唇が重なる寸前、ぐいっと反対側から身体を大きく引っ張られた。
キスを邪魔された佐伯が「チッ」と舌打ちする。佐伯から取り返した御堂を守るようにして、克哉が御堂の肩越しに佐伯に向かって声を上げた。
「何言っているんだよ、《俺》! ちゃんと御堂さんの自由意志で選んでもらうって約束しただろう!?」
「克哉……」
物静かで穏やかな表情を崩すことがない克哉が、御堂を奪われまいと強い口調で牽制する。露骨な嫉妬を見せる克哉の姿を目の当たりにして胸がじん、と熱くなった。
御堂を跨いで二人の佐伯克哉がにらみ合っている。どうやら自分がこの諍(いさか)いの原因らしいということは理解したが、御堂を取り巻く状況は理解しがたい。
そもそも、一体ここはどこなのか。大きなベッドを取り囲むように赤いカーテンが垂れている。ラグジュアリーなリゾートホテルの一室のようにも見えるが、それにしても窓もドアもないのはどういうことだろう。とりあえず、この部屋を調べようかと立ち上がったところで、二人に引き留められた。
「孝典さん、どこに行くんですか!」
「おい、俺たちを放り出す気か?」
咎める声に振り返れば、二人の佐伯克哉が並んで御堂に顔を向けている。二人とも同じシャツとスラックス姿で、受ける印象はまるで違うが、どう見ても二人とも佐伯克哉だ。
「いや、この状況を整理しようとだな……」
言い訳がましく釈明しようとしたところで、佐伯が眉をひそめた。
「俺が説明してやろう。あんたは《俺》か《オレ》のどちらかを選ばなければこの部屋から出られない。分かったか、御堂?」
「……いいや、まったく」
あまりにも不十分すぎる説明に、すがるような眼差しを隣の克哉に向けたが、克哉は慈悲深い顔をしながら諭す口調で言う。
「そういうことなんです、孝典さん。だから、選んでください。《オレ》か《俺》か。どちらが孝典さんの恋人として相応しいか」
結局のところ、御堂は二人の佐伯克哉のうちどちらかを選ばなくてはいけないらしい。だが、御堂は二人に向けて首を振った。
「そんなこと、選べるわけがない。君たちは佐伯克哉だろう?」
どちらかが偽物だということではない。二人がそれぞれ本物の佐伯克哉だということはすぐに分かった。佐伯に愛されている記憶はあるし、それと同じくらいの存在感でもって克哉を愛している記憶もある。それは間違いない。しかし、二人とも御堂の恋人の佐伯克哉だという確信はあるのに、自分がついさっきまでどちらの佐伯克哉と一緒にいたのかが思い出せない。
佐伯はレンズ越しの双眸を眇めて、ため息を吐きつつ言った。
「つまり、両方を選ぶと言うことだな」
「ああ。そうだ」
この状況でどちらかを選ぶことは、どちらかを捨てることになる。そんなことが出来るはずがない。となれば、『どちらか』ではなく、『どちらも』選ぶことが自分の気持ちに一番適(かな)っている選択に思えた。
「それなら仕方ないな」
「御堂さんの選択だしね。オレは受け容れるよ」
二人の佐伯克哉は顔を見合わせて頷く。そして、同じタイミングで御堂へと顔を向けた。なぜか二人の顔を見て、悪い予感がぞくりと背中を走った。
御堂は有無を言わせずにベッドの真ん中へと連れ込まれ、抵抗する間もなく二人に上半身を裸にされた。佐伯が自身のシャツの襟元のボタンを外しながら宣言する。
「じゃあ、俺からやらせてもらう」
「待てよ! ずるいぞ! オレだって孝典さんと……」
「俺はもう準備万端だ」
「それをいうならオレだって!」
すぐさま克哉の抗議の声が被って言い合いになる。御堂も巻けずと声を上げた。
「おい、私の意思はどうなっているんだ!?」
御堂そっちのけで喧嘩を始めようとした二人がハッと御堂を見た。
「確かに、どちらが先か御堂に選んでもらった方がいいな。それなら文句ないだろう、《オレ》?」
「……孝典さんが選ぶなら従うよ」
二人は納得したようで御堂の左右に身体を引いて、両脇に立った。
「孝典さん……」
克哉に左手をそっと取られて、乱された克哉のスラックスの前へと触れさせられる。そこには張り詰めた克哉のペニスが布地を押し上げていた。
「触ってくれますか、オレのを」
「君は……」
頬を赤らめてそんなことを言う克哉のベルトを外し、スラックスを脱がせた。淫靡な予感にこくりと唾を呑み込みつつ、せり出しているアンダーの上から克哉のペニスを、手でなぞり上げる。それだけで克哉は感じ入ったような熱っぽい吐息を漏らした。
込み上げてくる衝動に唆されるまま、克哉のアンダーをずり下げて弾み出てきたペニスを握った。それはもうすっかりと形を成していて、御堂は手の指で輪を作りゆるゆると扱き上げると、克哉の腰が揺らめきだす。
「御堂、俺のも忘れるな」
「え……?」
耳元で声がして、右手を掴まれた。そして、同じように佐伯のペニスも握らされる。それもすでに完全な屹立で、その硬さに息を詰める。抗えきれない眼差しに命じられるかのように、御堂は佐伯のペニスに指を絡めて扱き始めた。
ベッドに座る御堂を挟んで立った二人の勃起を握らされ、手淫させられている。頭上では熱っぽい吐息が漏れて、さらなる刺激をねだるかのように二本のペニスが御堂の口元にぐいと突き出された。
どうしてこうなってしまったのか。
理由を考えようにも、どうにも理解が追いつかず頭がクラクラとしてくる。
御堂の手淫によってあっという間に限界まで張り詰めたペニスは先端に蜜を滲ませていた。そんないやらしい形をした性器が二本、目の前で押し合っている。御堂は無意識のうちに顔を近づけ、二本の先端に舌を這わせた。同じ形、同じ硬さの性器、そして同じ潮気のある味が舌の上に広がる。
佐伯が快楽を滲ませた声で言った。
「先にイった方が負けだ。イかなかった方が先に御堂とヤるということでどうだ」
「いいよ。のぞむところだ」
克哉もまた勇ましい口調で受けて立った。御堂に選ばせると言っておきながら、随分と勝手な言い草だとは思ったが、それ以上に、自分の手や口で二人の佐伯克哉に快楽を与えることに夢中になっていた。
御堂は二本のペニスを扱きながら、亀頭を舐め上げて、くびれを舌先でなぞる。次第にそれだけでは満足できなくなって、同時に頬張るように口の中に迎え入れた。口いっぱいに音を立ててしゃぶり、一本ずつ深く奥まで咥え、他方は手でぐちゅぐちゅと濡れ音を立てながら根元から扱く。交互に口と手で奉仕すると、二人の膝が細かく震えて、刺激を必死に堪えているのが分かる。イかないように必死なのだ。
そんな二人を愛おしく思いながら、克哉の屹立を口にしたときだった。先端から溢れる蜜をちゅっと音を立てて吸い上げ、尖らせた舌先を鈴口にねじり込んだ瞬間、びくりとペニスが跳ねた。
「っ、ぁ……ああっ!」
克哉から快楽に屈っした悲鳴が上がった。
御堂の唇に重く熱い液体がぶつかる。びゅくびゅくと派手に噴き出すそれは、口の中に収まりきらず顔から胸まで散っていく。
濃厚な精臭にくらくらしながら、御堂は克哉のものを根元から先端まで扱き上げて、最後の一滴まで絞り出した。そして、口内に広がる克哉の味を確かめるようにゆっくりと嚥下する。
「孝典さん……」
克哉の精液を美味しそうに呑み込む御堂に、克哉は感じ入ったような声を出した。御堂と克哉の視線が熱っぽく絡まる。だがすぐに横から邪魔が入った。
「俺の勝ちだ」
そう言って佐伯が克哉を押しのけるように御堂との間に割って入ると、御堂をベッドに押し倒す。思わず抗議の声を上げた。
「おい、何をするっ」
「そういう約束だったろう?」
その約束は克哉と佐伯の間で交わされたのであって、御堂は巻き込まれただけだ。だが、佐伯は慣れた仕草で御堂のベルトを抜き去ると下着ごとズボンを引きずり下ろした。
「佐伯、よせっ」
「なんだ、あんたももう臨戦態勢じゃないか。俺たちのを舐めて、浴びせられて、気持ちよくなったのか?」
「――っ」
揶揄する声に顔を赤らめた。下着から弾み出たのは、鋭角に頭をもたげてぐっしょりと濡れている性器だ。羞恥にベッドの上を這いずって逃げようとしたが、佐伯に腰を引き寄せられた。
「……ぁ、」
佐伯に向けて腰を掲げる体勢にされると、アヌスに佐伯の指が挿りこんできた。あっという間に解されて、佐伯の屹立が押し当てられる。慌てて声を上げた。
「ちょっと待て……っ」
「待てない」
「ぁ、ああああっ!」
無慈悲な言葉と共に圧倒的な質量がぐぐっと窮屈な場所にねじ込まれていく。シーツに爪を立てて、声を上げ続けるが、佐伯は巧みに腰を遣いながらつながりを深めていった。
獣のような体勢で犯される。身体を割り拓かれる苦痛に呼吸を短く刻むが、御堂が感じるのは痛みだけではない。苦しさを凌駕する気持ちよさが急速に込み上げてくる。抱かれる苦痛もその後に続く気持ちよさも、御堂にとっては馴染み深いものだ。
尻肉に克哉の熱い肌が押し付けられた。根元まで自身を埋め込んだ佐伯が滑らかに腰を遣い出す。体内を佐伯の形に拡げられて、深いところの快楽の凝りを擦りあげられて、先端からとろとろと蜜が零れ始めた。艶めいた喘ぎが御堂の口から漏れ始めた。御堂の身体の隅々まで知り尽くした動きはまさしく恋人の佐伯そのものだ。
「ふあ……、あ、んあっ」
「俺に抱かれるのは気持ちいいだろう、御堂?」
胸の前に伸びた佐伯の手に、赤く色づいた乳首をきつく摘ままれながら、そう問われる。まともな返事が出来ないほどの甘ったるい疼きに襲われて、御堂は返事代わりにガクガクと頷いた。
背後の佐伯は満足げな吐息を漏らし、御堂の腰を掴み直すと御堂の身体ごと後ろへと重心を傾ける。背面坐位の体勢にされ、ベッドに押し付けていた顔の前に視界が広がった。目の前にいる克哉とまともに視線がぶつかると同時に、自重で腰がさらに深く沈み込む。
「や、ぁ――っ」
佐伯の太いものに貫かれている結合部も、それに感じきって臍につくほど反り返った自身の性器も、何もかもが克哉の前に晒される。御堂を見つめる克哉の眸が大きく見開かれ、唾を呑み込んだのか形の良い喉仏が上下する。背後で佐伯が喉で低く嗤った。
「ほら、あいつに見せつけてやれ」
「よせ……っ、見るな……克哉っ」
首をぶんぶんと振って拒絶したが佐伯は容赦なかった。大きく開かされた両脚の付け根、克哉の怒張を深く咥え込むために拡がったアヌスを克哉に鑑賞される。いくら二人が同一人物で、どちらも恋人の佐伯克哉だとしても、苛烈な羞恥に頭の芯が焼き切れそうになる。しかし、一方で克哉の視線を感じて、御堂のペニスはとぷりと大量の蜜を溢れさせた。
克哉が熱っぽい眼差しを向けながら、御堂の元へと身体をすり寄せた。
「オレも混ぜて……」
「克哉……!?」
克哉は御堂に艶やかに微笑むと、そのまま御堂の股座(またぐら)に頭を伏せた。口を大きく開き、御堂のペニス咥えると、唾液をたっぷり塗しながらおいしそうに音を立ててしゃぶり出す。克哉の口淫にしびれるような疼きがペニスを駆け抜ける。
「ん……っ」
「邪魔するな、《オレ》!」
佐伯が不満げな声を上げたが、克哉はそれを無視して御堂への口淫を続けた。
後ろからは佐伯に犯され揺さぶられ、前からは克哉が舌と頬の粘膜で御堂のペニスを扱き上げる。
上目遣いに御堂を見上げる克哉と視線が結び合った。ぞくりとするほどの悦楽が背筋を貫く。それは克哉にも伝わったのか、御堂のペニスを口いっぱいに頬張って、苦しいながらも恍惚と眸を潤ませる。克哉へのたまらないほどの愛おしさが込み上げて、懸命にしゃぶる克哉の頭に手を置いた。
「ぁ……、んっ、か…つや……」
酩酊するほどに快楽が高まり、極みまであと一歩……というところで唐突に背後の佐伯が動きを止めた。突如中断した行為に克哉もまた動きを止めて、頭を上げる。
一方の御堂は絶頂寸前のところで放り出されて、遠のいた快楽に「ぁあっ」と思わず切ない声を漏らしてしまう。
佐伯は御堂の肩越しに顔を出して、克哉に向けて怒ったような声を出した。
「勝手に割り込むな。図々しいぞ」
「別に邪魔はしてないだろ!」
ふたたび御堂そっちのけで喧嘩が始まるのかと思いきや、佐伯は舌打ちをすると御堂の中からずるずると自身を引き抜いた。
「興が醒めた。順番を譲ってやる。俺は後からじっくりいただくさ」
「は……?」
佐伯は御堂の背後から身体を退くと、代わりに克哉の手を引っ張って身体をぐいと引き寄せた。よろめいて倒れ込む克哉の身体を佐伯が抱き留める。
「手伝ってやる」
「な……《俺》! おいっ!」
「俺が手伝ってやると言ってるんだ。暴れるな」
バランスを崩した克哉の慌てふためくつま先が空を蹴った。だが佐伯は手慣れた仕草で、先ほど御堂にそうしたように自分の脚の間に克哉を抱きかかえるようにして、両脚を大きく開かせる。そして御堂の見ている前で克哉のアヌスに指を這わせた。
「やめ……、ぁっ、あ……っ」
佐伯は克哉のアヌスを揉み込むようにして撫でながら、潤滑剤で濡れた指をつぷりと潜り込ませた。そして、二本、三本と次々と指を挿入していく。くちゅくちゅと濡れた音が立ち、着々と下準備が施される。克哉はいつの間にか抵抗をやめていた。それどころではないのだろう。佐伯に与えられる刺激に内腿を引き攣らせながら、手の甲を口に当てて必死に声を堪えている。
同じ顔をした男二人の淫らな様子に、御堂は目が釘付けになる。御堂の中には中途半端な快楽が昂ぶったままで、いやらしく睦み合う二人へと誘われるようにじり寄っていく。
「孝典さん、見ないで……」
克哉が恥ずかしさに泣きそうになりながら、御堂の名を呼んだ。背後から克哉のアヌスを指で犯す佐伯が御堂に向けて悪辣に笑いかける。
「ほら、御堂、食べ頃だぞ?」
「――ッ」
佐伯が粘膜をめくり上げながら指を引き抜いた。柘榴色の粘膜が覗き、その淫猥さに理性が吹き飛んだ。衝動に唆されるまま克哉のアヌスに自身の屹立を押し当てる。
「ぁあああっ」
背後からがっちりと佐伯に押さえ込まれた克哉は、白い喉を反って声を上げた。その喉に御堂は噛みつくようにキスをする。腰を差し込み、窮屈な内腔を押し広げながらじわじわと自身を進ませていく。
「ぁ……、あ、あ…っ、孝典さんの、きつい…」
克哉が嗚咽まじりの哀切な声で訴えてくる。その顔にも声にも煽られるだけだというのに、克哉はそれを無意識でやるから余計にたちが悪い。
一番太いところをどうにか呑み込ませると、いくらか抵抗が楽になった。
腰を細かく前後させながら根元まで呑み込ませると、背後から克哉を支えていた佐伯が腰をねじるようにして身体を抜いた。支えがなくなった克哉をベッドに押し倒すようにして覆い被さる。克哉が逃げられないよう押さえ込んで、したたかに律動を始めた。
「ぁ、あ、は……ぁん」
御堂に馴染んだ粘膜が絡みついてくる。深いところからぶわりと沸き立つ快楽を追うように、忙しなく腰を打ちつける。
激しく揺さぶられる克哉が両手を御堂の背に回した。引き寄せられるようにして唇を合わせる。口と下半身の粘膜でつながりながら官能を分かち合うセックスに、脳内に火花が散った。どこまでも深いところで交わろうと腰を強く打ちつけたところで、御堂はぎくりと動きを止めた。異変を感じた克哉がおずおずと唇を外して声を出す。
「孝典さん……?」
「……っ」
「いやらしい姿だな、御堂。そろそろ俺も混ぜてもらおうか」
すぐ背後から佐伯の声が響いた。抗うよりも早く克哉の指が御堂のアヌスを犯す。そして、そこが柔らかくほぐれたままであることを確認すると、指が引き抜かれ、代わりにもっと硬く太いものが侵入してきた。
「嫌だ……っ、佐伯っ!」
不埒に割り込んでくる佐伯を拒もうとしたが、先ほど佐伯に馴らされた隘路は、ぐずぐずに蕩けて怒張を受け容れていく。
逃げようにもペニスを克哉の粘膜に挟まれて、後ろを佐伯に穿たれて、どこにも逃げることが出来ない。
「ひっ、は……ぁっ、あ」
佐伯のものに粘膜をごりっと抉られて、克哉の中に収めたペニスがびくりと跳ねた。
後ろからの刺激に興奮して、硬さと太さを増したペニスが、克哉の中を強く抉る。
「ぁ、孝典さんの、大きくなった……っ」
「ほう、そんなに良いのか」
「違……っ」
否定しようにも克哉が正直にそんなことを言うものだから説得力がない。佐伯は低く喉で笑うと猛々しく律動し始めた。佐伯の腰の動きにつられて御堂もまた克哉の中を突き上げてしまう。
克哉を犯しながら、佐伯に犯される。二人に挟まれて、少しでも腰を動かそうものなら、乗算された快楽が前からも後ろからも御堂を襲った。
「っ、ぃ……、ぁ、あ……、はぁっ」
「孝典さん、どうしよう、すごく気持ちいい……」
克哉が極まったように御堂を抱きしめながら、腰を貪欲にうごめかす。背後から御堂を犯す佐伯と息を合わせるようにして、御堂のペニスを熱い粘膜で揉みしだいてきた。
荒波に翻弄される小舟のごとく自分では制御出来ない悦楽にもみくちゃにされる。開きっぱなしの口から、声にならない声と涎が溢れた。それを克哉が舌を伸ばして舐め上げていく。思わず克哉の舌を啜るようにして口を重ねた。
唾液を混ぜ合わせるようにして熱っぽくキスを交わす御堂の耳元で低音の蠱惑的な声が響いた。
「妬けるな……」
「――ッ」
佐伯に耳朶をねっとりと舐め上げられて食まれる。耳の穴まで犯されているかのように舐(ねぶ)られて、ねじくれた官能に意識がぐつりと煮え立った。
御堂にのしかかる佐伯の腰の動きがぐっぐっと細かいリズムを刻みだす。射精に向けた動きだ。引きずられるようにして、御堂も絶頂に向けて一直線に上り詰めていく。
三人の快楽が昂ぶりきったその時、克哉の粘膜が波打つように戦慄いた。
「ぁ、あ――っ」
御堂と克哉の腹の間に挟まれた克哉のペニスが跳ねて、びゅくりと白濁を噴き出した。絶頂にきつく引き絞られた克哉の粘膜に御堂もまた息を詰めた。限界まで膨らんだ快楽が弾ける。
御堂は背をしならせて、克哉の奥深くにどっと放った瞬間、御堂を犯す佐伯もまた低く唸って御堂の最奥に重たい粘液を注ぎ込んだ。
目も眩むような快楽に身体を引き攣らせる。絶頂の波はなかなか引かず、誰かが少しでも身体を動かす度に引き戻される悦楽に悶えうった。
ようやくまともに呼吸が出来るようになったころ、しっとりと汗ばむ肌に四本の腕が巻き付き、克哉と佐伯の身体が密着する。そして、同時に告白された。
「孝典さん、あいしてます……」
「御堂、あいしてる」
この上ない幸福感と快楽に包まれながら、自分の真下にいる克哉、そして、肩越しに振り返った先にいる佐伯と一人ずつ視線を重ねる。どちらの佐伯克哉も間違いなく御堂の恋人の佐伯克哉だ。その二人に愛を捧げられる幸せを噛みしめるようにして告げた。
「私も、君たちを愛している」
御堂の言葉に克哉も佐伯も嬉しそうに微笑む。互いに視線を交わし、そしてまた身体を蠢かせた。それはすぐに淫らな動きとなり、重ね合わされていく。遠のきかけた快楽はさらに大きな波となって三人を呑み込んでいった。
ハッと御堂は目を覚ました。
御堂はベッドの上で、部屋の中には薄く青い光が広がっていた。
夜が明ける前の静謐に満ちた時間帯だ。
がばりと御堂は上体を起こした。裸の胸に手を当てると、興奮冷めやらぬ心臓が未だ乱れ打っている。
もう一度部屋の中を見渡して、ここがあの赤いカーテンに囲まれた部屋でないことを確認し、安堵の息を吐いた。
やはりあれは夢だったのだ。
「馬鹿馬鹿しい……」
呟いた声は掠れていた。まるで先ほどまで声を上げ続けていたかのように。
それでも、あんなことが現実にあるはずがない。御堂の恋人である佐伯克哉が二人いて、佐伯克哉を抱きつつ抱かれるなど……。
その時に感じた嵐のような快楽を生々しく思い出しそうになり、御堂は頭を振って自らを落ち着けた。
――私の恋人は佐伯克哉、ただ一人だ。
ベッドの傍らへと視線を落とした。そこには御堂に背を向けるようにして、恋人の佐伯克哉が安らかな寝息を立てている。
愛しい恋人の姿を目にして御堂は満たされた心地になり、眠りを分かち合うためにふたたびベッドへと潜り込んだ。すぐさま、まどろみの中に意識が沈んでいく。
そして、意識が眠りに落ちる直前、どこからかふわりと漂う甘酸っぱい果実の香りを感じた気がした。
END